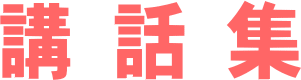
(毎月発行の『連絡紙』より)
| ●平成16年6月号 |
| ジャイアント馬場の七回忌が行われた。死人を鞭打つつもりはないが、同じプロレスラーのジャンボ鶴田も馬場と同じように肝臓が悪かった。彼は臓器移植の手術に失敗して亡くなった。対して馬場は命を神に任せたまま、最後までプロレスラーとして生きた。馬場の馬場らしさだと思う。 馬場は新潟県が生んだ偉大なプロレスラーだった。だがそんな事よりも、何より偉大な哲学家だったと筆者には思える。そして馬場のそんな哲学を形作ったものは何でもない、ただの痛み・ただの恥ずかしさだったように思う。今月は馬場の偉大さ・悲しさについて書いてみたい。 馬場のことを世界の偉大な巨人とか、気は優しくて力持ち、とかマスコミは言っていた。だがそうではない。マスコミは痛みを避けた話をするしろものだ。だから表面だけしか考察しないしマト外れのコメントや見方をしたがる。 偉大な巨人を見たくて馬場のファンになった人は少ないと思う。筆者に言わせたら、リングに立つだけでプロレスだったのだ。馬場しかできないプロレスだった。それが時代遅れ(多分大きく遅れてしまったプロレスだった)でドン臭いプロレスであっても観衆を魅了した…それが馬場だった。 それだけの力が馬場にはあったのだ。馬場の場合、魅了する力とは生きざまだった。ドン臭かろうと大昔のプロレスであろうと馬場の生きざまを見に、ファンの多くはリングに集まったのだ。ただ強いだけならあんなにファンは集まらなかったはずだ。ラッシャー木村というプロレスラーは敵対しつつも「オレは馬場さんが好きだ」とリング上で公言していた。筆者もそう思うが、馬場にはそれだけ人間の魅力があった。 だがその魅力とは格闘家にしては余りに静かすぎるものだった。 「一日じゅうただ黙って海を見ている…それが幸せです」とは馬場の言葉だった。実際、ハワイにコンドミニアムを買ってそうしていたようだ。そんな事を幸せと言うだけ、馬場の幸福観はいろいろなものを切り捨てて来た結果で成り立っていたのだ。正確には切り捨てさせられた結果なのだ。 馬場の人生観はまず、大きな恥ずかしさで培われたのだと思う。大きな恥ずかしさの一つは巨体だったことだ。身長を武器に戦ったというのはマスコミだけだ。 馬場にとって身長とは恥ずかしさでしかなかった。 「プロレスラーと言うけど所詮自分は見世物ですよ」と言ってもいた。一番の辛い部分を晒さねば生きられなかった辛さがそこにある。 体の恥ずかしさは努力でどうこうなるものでない。その分、諦め得たとしても決して慣れないものだ。それを商品として位置付けて自分を勇気づけたのだ。だから常に悲しい顔をして戦っていた。テレビでしかないが、ギラギラした顔を筆者は見たことがなかった。戦う顔とはアントニオ猪木のように、恐怖と気張りの混じった顔なのに、だ。 馬場の哲学を作った要因は幾つもの痛みと挫折だ。運がない人だった。軌道に乗り出すと失敗という事の繰り返しだった。そしてそれが馬場に「現実は受け入れるもの」という事を教え込ませた。あれだけの成功を収めた人と言うかもしれないが馬場にとっては成功も不成功も無意味で、ただ現実を受け入れようと自分と戦うだけで精一杯だったのだ。 馬場の人間性は醸し出されたものだ。醸し出したくて醸し出したのではない。自分と戦うだけで精一杯の結果で、自然と生まれたものだった。神慮の気まぐれに蹂躙されつつも常に大まじめに現実を受け入れ、その現実と取り組み、取り組む為に自身を叱咤して来た結果なのだ。そして…現実を逃げずにいれば私達も馬場のように自分だけのリングに出会えるのだ。 |
|講話集トップへ戻る| |
/トップ/定例活動/特別活動/講話集/今月の運勢/@Christy/