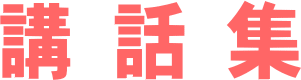
(毎月発行の『連絡紙』より)
| ●平成17年11月号 |
| 筆者がまともに家にいるのは日・月・金曜日である。後の四曜は外出している。木曜日は新潟みなとトンネルで歩きの鍛錬をやっているし、土曜は泊まりで滝打たれに行っている。歩きの鍛錬では足の筋肉からと心臓がきしむ。それでも目をつぶっても無理やり手を振って歩き抜く。そこまで自分を追い詰めねばやったことにならないと考えている。土曜の滝打たれは文字通り命懸けだ。これから益々打たれづらくなって行く。滝打たれは決して慣れることはない。打たれる回数が増すのに比例して嫌な思いが段々強くなっている。いつかその嫌な思いに自分が立ち往生するだろうし、その時が滝を止める時だと予感している。 それでも筆者はそんな生活が楽しい。社会の多くは「そこまでしなくても」と思うらしい。もっと楽して楽しくやれることが沢山あると考えているらしい。だから筆者のような生活は「わざと難儀をしている」と思われてしまうようだ。とにかく筆者などは「なにもそこまで」と思われるのは当然なようで、ある種の変人に見られているようだ。 筆者が変人とみられるのは仕方ないとして、でも「なにもそこまで」と思うのは間違いだと思う。 筆者が行者だから好んで難儀をしていると考えるのも間違いだ。必要に応じた事がたまたま難儀なことになる場合はあっても、好んで難行をしたって立派な行者にはなれない。立派な行者に何よりも必要なものは霊的な資質ではなく、ありきたりの心なのだ。この点は滝場で良く言っていることだ。ただ必要であるならば難儀は厭わないだけだ。必要なことに集中してゆく、それが回りから「なにもそこまで」と思われるようだ。 「そこまでしなくても」人生は楽しく楽に生きることができると多くの人は考えるようだ。だがそうだろうか? 滝打たれを十七年間続けて来て言えるのは、人間は味わうために生きているのであって、楽するために生きているのではないということだ。しかも安心して味わえるようになっているのだ。 では何を味わうのか…それを簡単に言うと喜怒哀楽という事である。この喜怒哀楽を味わう事を別の言葉で言うなら、自分の生きて行く哲学の確認確信ということになる。哲学の確認確信を簡単に言えば、自分を感じ続けるという事になる。人生の風景の中で自分を感じていれば、それを明確に感じれば感じるほど、たとえそれがどんなに悲惨な風景でも、快いように人間はできているのだ。 今の自分を明確に感じ取るとは自分で自分を意識することではなく、自分のエネルギーを感じとることだ。自分で自分を意識できる時は集中などしていない。意識で自分を捉えている間は、その自分は曖昧な自分だ。自分を明確に感じ取れる時には自分が無くなっている。要するに集中していなければ明確な自分ではないのだ。更に言うなら集中するという事は一所懸命でなければ到達できない境地だ。 境地というと難しそうだが、境地というものは心で同じ実感が繰り返せるという事でしかない。その繰り返しが一所懸命でありさえすれば得ることができるのだ。 一所懸命であれば自分を明確に感じ取れるし、自分が明確であることが人間として授かっている快さの正体なのだ。つまり一所懸命でさえあれば、私達は知らず知らずに人生の風景を余すところ無く味わい、快く生きて行かれるのだ。 社会では多くの人が、努力とか頑張りとかを結果と結び付けるし、その結果というものは楽で楽しいものを意味させ、それを幸せと錯覚している。だが楽で楽しいものだから私たちは執着するし、執着した分だけ不安を強くして生きている。「なにもそこまで自分をいじめなくても」という人は快さと幸せの違いに気付くべきなのだ。 |
|講話集トップへ戻る| |
/トップ/定例活動/特別活動/講話集/今月の運勢/@Christy/