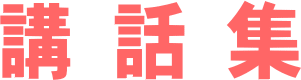
(毎月発行の『連絡紙』より)
| ●平成17年7月号 |
| NHKの朝の連続ドラマの「ファイト」が良い。主人公役以外の役者の演技下手が気になるが、しばらくぶりの良い台本だと思う。 このドラマの五月の第三週では、主人公の「優」という女子高校生が登校拒否となった。父親の仕事上のことで仲間外れになっていた優だったが、一緒にその高校に行った親友のいる仲間のグループに戻れた。「もう友達を失いたくない」とつくづくと思った優だったが、嘘をついていたのがその親友だとわかった。すると仲間は親友を仲間外れにするようになった。優は仲間から再び孤立することが怖かったが、親友を仲間に戻したくもあった。だが何もできず、親友の孤立する様を見続けるだけだった。そしてそんな学校に足が運べなくなり登校拒否となったのだ。 我々の子供の頃と違って現代の子は小さな事に気を使い過ぎる。我々の頃は学校へは行くものにしていて、どんなに嫌なことがあったもその前提に疑問を感じなかった。それだけ我々の子供時代はまだ画一的であったが、やるべき事が見えた時代だった。というか明確な自己というものを持たなかった。だから学校へは行くもの、と単純に信じ込めたのだった。現代の子は自己を確立せねば生きて行けない状況にある。ささいな事でも見逃さない、いや見逃せばそれがたまりにたまって大きな自己矛盾となって現れて、そしてその自己矛盾から自分らしさを見いださねばならない…。そんな時代だ。 さてこのドラマで、登校拒否の優に対して、父親が「学校へは行くものなんだ。どうしても学校へ行け」と怒鳴るシーンがあった。 台本の間違いだ、と筆者は思った。そのように怒鳴るのは(いや怒鳴らなくても)行く物として決めつけて疑問に思わないのは殆どが母親なのだ。刹那的、直接的なのは男より断然と女だからだ。さらに言えばこの刹那的直接的な結論の多くには「社会通念」以外に何の根拠もない場合が多いのだ。ドラマでの「学校へは行くものなんだ」というせりふは「社会通念」以外に何の根拠もない事の代表だったのである。 この父親は学校へは友達を作るために行くものだと優に説いた。果たしてそうだろうか?。筆者の高校生活は大先生が倒れておられたから、全日制でいながら定時制生徒に似たようなものだった。それでいていつ辞めても良いという思いで三年も通ってしまった。そんな筆者なのに、なぜ学校にゆかねばならないかについてはドラマのように明確に答えられる親にはなれていない。…まさに我々の時代の親であって、子に蔑まれる親なのだ。 子に蔑まれるのは、先に書いたが自己が不明確だからだ。不明確な分、便利を生み出して生きていると錯覚してしまう。だから大きな会社の社長であっても、立派な立場にあっても、子だけではなく若者からどこかあざけり笑われてしまう。若者とどこか距離を感じるものの、それでいてそれを埋めて行く「本物」たる自信がない。自己が不明確でも生きて来られたのだから、自信がなくて当たり前だ。現代の若者のひいきをする訳ではないが、これからはいや元来人間は、自己を明確にせねば生きられないのだ。学校へは行くもの・稼ぐことは正しいなど、何の根拠もない事(その根拠が正しい時代もあったかもしてないが)を「ああそうですか」と受け入れられる方が間違っているのだ。 登校拒否の問題を教会ではよく受け、学校に行きさえすれば良いという刹那の解決を求められる。だが子は行かない理由が無くなれば復学するのだ。回りの人と同じに区切りをつける事も根拠の無い事なのだ。だから親はただ黙って子の悩む様を見守るしかない。だが自己の確立という点で死ぬまで悩まねばならないのは親でも子でも同じで幸せや便利では代えられないのだ。 |
|講話集トップへ戻る| |
/トップ/定例活動/特別活動/講話集/今月の運勢/@Christy/