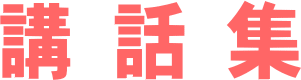
(毎月発行の『連絡紙』より)
| ●平成18年3月号 |
| 教会では個性とか命とか言い、それらが何物にも優先する価値であると説く。個性とか命というとなんとなく理解されるようだが、その実、具体的には何が個性なのか判らない。具体的に判らないが判らなくても個性とか命が何者にも優先されるには変わらない。 判らないが優先されることは判るから大事にする。だが大事にするということは安全無事な場所にて保管することではない。逆に徹底して酷使することなのだ。酷使して行く経過で哲学が生まれる。哲学が生まれないならば酷使とは言えない。哲学は個性とか命を大事に使うのに鍵となるが、その哲学は容易には生まれ得ない。 遺伝子の研究が盛んになって、個人を決定する要因は遺伝子であることが判ってきた。個人とは遺伝子の決めた寿命や感性であり、要するに先天的な資質であって、この先天的な資質は生理的にも精神的にも唯一無二なるものであるということなのだ。 だから遺伝子を同じに組み立てることができれば、クローン動物・クローン植物と言われる複製の固体ができるし、現実に出現もしている。また自分を形作る幾つかの遺伝子の、その内の弱った遺伝子を新しい同じ遺伝子と入れ替えれば、不老長寿の自分を作ることが出来る。だから遺伝子をイコール個性とか命とかに考えてしまいがちだ。だが人間は遺伝子などの先天的な要素だけで決定される単純な存在ではない。 クローン動物を見ると人間が遺伝子などの先天的な要素だけで決定されない事が良く判る。現実のクローン動物は、例外なくひ弱に出来ている。このひ弱こそが遺伝子をイコール個性とか命と呼んではならない事の証明なのである。 同じ遺伝子を持って生まれながらひ弱なのは、誕生後の「経験」に違いがあるからだ。同じ遺伝子で同じ経験を積み重ねたなら同じたくましい種をまっとうできるのかもしれないが、現実のクローン動物は人工飼育の世界にいる。だからどれほど優秀な遺伝子を持って誕生してもひ弱となる。ひ弱を正確に言えばクローン羊は見た目だけ羊で、実は羊という「種」でない事を意味する。 つまり人間の資質を決定するのは遺伝子だが、遺伝子が十分に働くにはその遺伝子にパワーが備わってなければならない。そして遺伝子がパワーを持つには後天的(生きる行為)に何かが必要ということになる。 では問題の後天的に必要なものとは何か?それはクローン動物の人工飼育が証明している。人工という保護された環境ではせっかくの優秀な遺伝子もひ弱さに消されてしまうのだ。遺伝子が健全に機能する力は人工でないこと、つまり現実から逃げずに生きる事からしか生まれないのだ。生きるとは苦痛を受けるという事と同じ意味である。人生は生老病死という展開になっていてこの展開から苦痛を受けなければ私達は人工飼育のクローン動物と同じで、ひ弱な存在となる。 この生老病死という展開の多くは苦痛でできていて、その苦痛を強く受ければ受けるほど、遺伝子に強いエネルギーを持たせる事ができてしまう。正確に言えば生老病死だけではなく、喜怒哀楽の感情の一切が遺伝子にエネルギーを持たせるものとなる。そして更に言えば、楽しいとか楽だとかいう感情はほとんど必要ではないのだ。 現実の百の内九九が不満足で作られているのはこの事の証明だ。逆に百の内九九が満足で作られてしまったら、人工飼育と同じになってしまってせっかくの遺伝子が腐ってしまう。遺伝子にエネルギーを持たせる喜怒哀楽の感情の積み重ねを哲学とも言う。つまり哲学が遺伝子にエネルギーを持たせる。…懸命に生きるとは不満足としっかり対峙することでしかなくただ熱く生きるだけなのだ。 |
|講話集トップへ戻る| |
/トップ/定例活動/特別活動/講話集/今月の運勢/@Christy/