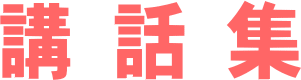
(毎月発行の『連絡紙』より)
| ●平成18年6月号 |
| NHKの朝の連ドラ『純情きらり』について。主人公はジャズピアニストになって行くのだろうか。 五月十六日放送での事だ。主人公は来年の芸術大学合格の為に奮闘している。試験の審査官でもある教授の下にピアノのレッスンに通っているのだが、レッスン仲間から「貧乏人は音楽家になれない」と断言された。主人公は「なってみせる」と一層の努力をして曲をマスターしたのに、教授から「楽譜どうりで面白味も色気もない」と評されてしまう・・・。以前にも主人公が試験に落ちたとき、教授からあの時は「あの時はピアノを楽しんでいませんでしたね」といわれるシーンがあった。 以前、このコラムで、落語家の立川談志の「クビ」になった弟子達が合同合宿をして演芸会を開催することについて、合同練習自体が間違っていると書いた。落語家は同じ演目でも囃手が違うとまるで違って聞こえるが、それが囃手の味というもので、だからと合同練習する位なら自分というオリジナルを磨けばよいと書いた。 五月十六日の朝ドラも同様な事を言いたかったのだ、と筆者は思う。レッスン仲間に負けたくないという思いで頑張って、仮に勝ったとしても所詮は自分を見失うだけで、だから面白みも色気もないと評された。 絵画の世界では、有名な先生の門下にならないと評価が得られず評価を得られないと食っていけないから、全く毛色の違う先生であってもその門下にしてもらう。でも考えれば判ることだが有名な先生の門下になる事と評価を得ることとは全く別の事だ。 絵なら絵の評価を下せるのは専門家であって、見る人の総体ででないというのは矛盾でおかしい。展覧会に入選したから良いとばかり言えないのだ。筆者の偏った美意識で言うのではないが、専門家の評価より自分の評価が絶対に正しいのだ。 専門家の評価を絶対とするなら芸術の楽しみ方は一方向とか数方向からしかない事になる。そうではない。人数分だけの評価があって当然なのだ。 谷村新二という歌手がいる。中国の音楽大学の教授でもある。彼の授業は音楽については何も教えないで、あの小説・この話で終わるという。人間性を豊かにしなさいと彼は暗に示しているのだ。 あれは阿賀野市の恥だったと思っている事が筆者にはある。最後のゴゼと言われた小林ハルさんの事だ。小林さんは胎内市の施設に入ってから評価が高まったのだが阿賀野市におられたときには否定されていた。いわく「離れゴゼだから評価すらできない」というのが専らだった。そうではないのだ。良いと思えたらそれは良いものなのだ。一人や二人が小林さんを否定するならそれも有りだが、多くが否定し蔑んだ。それが恥なのだ。 系統づけねば評価できないという間違いは自分の感性に無関心だからできる事で、悲しいことだ。良いと思ったらそれで良いのだ。なぜなら感性とは個性のことだからだ。個性とは否定されようと評価されようと、そういった価値とは全く無縁な、ただ受け入れざるを得ないもの、なのだ。受け入れざるを得ないから、命でもあるのだ。さらに言えば、命だから生理的な命以上の存在なのだ。 私達は自分の感性に自信をもつ生き方をすべきだ。それには自分の都合や思いで今を選ばずに、ただ一生懸命に生きることだ。過去未来に唯一一人である自分を受け入れられなければ自分の感性に自信は持てない。自信を持たないでどうして命を使ったと言えようか。 滝は脳幹部を逞しくする。原始な存在の脳幹部が逞しいとは感性豊かの証だ。だから滝に打たれれば自分の才能は豊かになる。が、磨く事と豊かである事とは違う。磨くのは生き方に因るのだ。磨く生き方をせねば自身は持てない。 |
|講話集トップへ戻る| |
/トップ/定例活動/特別活動/講話集/今月の運勢/@Christy/