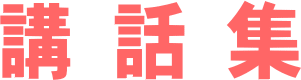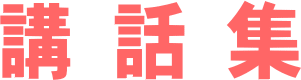|
教会では出発(タビダチ)祭が行われた。出発祭は正式には産土大国(ウブスナ・ダイコク)祭と呼ばれ、産土神と大国主神に感謝と誓いが披瀝される。披瀝された色々な感謝と覚悟に人それぞれの思いを見てしまう。節目に何を思うかに人の生き方が見えてくる。披瀝する内容が覚悟なのか願いなのかによって大きな差が出てくる。
人を救う神は低級な神である、と筆者は言う。神は古代では人の邪魔をする存在だった。人の邪魔を『祟る』と称したから古代の神は祟る存在だった。そした暴れ祟らないように祀った。今もアイヌの人達は新しい出会いに対しては風景・動物・自然現象の別なく、その存在を神と認め、暴れ祟らずにいて自分達と共存してくれるように供物を供えて祀っている。
これは字にも表れている。祟るという字と崇拝の崇の字は良く似ている。困った現象が「出て示される」のが祟である。その困った現象とはつまり人間の邪魔をする存在=神であり、神は高い所に住むから「山」を「畏怖する気持ち」になる…それが崇である。つまり祟と崇は裏表なのだ。
それ程に神は人間の事を何とも思ってはいない。神は人間の安楽など問題にされてはおられない。
歴史的に見て、祟る存在の神が人を助ける・救う存在に変質するのは仏教伝来からだ。一切無という釈迦の教えが概念・イメージである為に、その概念を説く方便として幸せと仏をつなげたに過ぎない。本当の幸せとは一切無を受け入れて安心する事だが、本当の幸せでない幸せもある。それは人間個人の思い願いが叶う事であり、それも仏が叶える、と方便した…。
個人の思い願いが叶う幸せとは好都合をしか意味しない、と本教では言う。思い願いが叶わない事を不幸というが、不幸の実体は不都合でしかない。好都合不都合とは別の所に生きる行為がある。幸不幸は単に風景に過ぎないのだ。
その風景は圧倒的に不都合が多い。百の内一つが幸せなら満点だ、と本教が説くのはここにある。太古から神は祟るもの、神は人間の思いや願いの邪魔をするものだから、それも当然なのだ。
圧倒的に不都合が多いのははっきり言えば、幸不幸は人生の枝葉でしかない。だがこの事を多くの人は分からない。生きる事は幸せの追求と断ずる人すらいるのが実情だ。
そういう人ほど、じつは愛されて育っていない。親の都合で慈しまれたり邪魔がられたりして育って来た。都合で可愛さの変わる愛が悲しいかな日本人の愛なのだ。都合で可愛さの変わる愛は親子関係にのみ限らない。夫婦でも恋人同士でもそうだ。仏を自分の思いや願いの使いっ走りに使って疑問に思わないのだから、当然と言えば当然である。神は元々が人の邪魔をする存在なのに、自分の思いを叶える神が良い神でそうでない神は邪神と断ずる。
人間が皆持っている悲しさすらも不幸という。赤ん坊が泣いて産まれてくるのはこの悲しさ故だ。
産まれなければ悲しくなんかならない。人間が皆持っている悲しさとは一切一人という事だ。人間は一人で産まれて一人で死んで行く。その間、自分というイビツな部分(=個性)に翻弄されて死んで行く。イビツな部分は他人のイビツを真似て得たとしても全く無意味だ。どんな幸福を手にしたとて、自分しか分からない・自分しか処断できない世界があって、その世界こそ自分の覚悟でしか突破できないのだ。家庭や家族を大事にする人を偽物と評するのはここに訳がある。家庭や家族が大事な人は自分の覚悟ができていないのだ。妻や子に「それはお前が判断して解決する事だ」と言えぬ男は悲しい。自分で判断して解決すべき一切一人の世界に対して回りの助力を求めることもまた悲しい…。自分の覚悟を哲学とも言う。
|