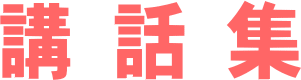
(毎月発行の『連絡紙』より)
| ●平成21年11月号 |
| 日本文理高校の野球部が夏の甲子園のスターだった。惜しくも準優勝ではあったが、けれんみのない戦いぶりは絶賛されて当然だった。自信を持つことが教育と筆者は訴えるが、文理野球部員は大きな教育を受けたと言える。弱くはなかったが、果たして強かったのかと問えば筆者には疑問に思える。結果も感銘も一緒くたにするマスコミの報道態度に抵抗があるから敢えてここで主張させてもらうのだが、文理野球部が本当に試合をしたのは準決勝の岐阜商業戦だけではなかったかと思う。一戦目は相手チームの継投ミスだったし、二戦目は手の内を知っているチームだったし、三戦目はインフルエンザで代わりのピッチャーがいなかった。決勝戦に至っては大差の勝利を確信した相手チームの緊張の緩みが原因であそこまで追い詰めることが出来た。運も実力のうちとは言う勝ち方は一戦の勝利に対して言うことで、文理はそれとは次元の違う正当な勝ち方ではあった。が文理野球部は確かに力があったが、やはり勝負には運の流れがあってそれにうまく乗れたのも事実だと思う。 今月は文理野球部の上手下手を言うのではない。ただマスコミの無責任な評価に文句を言いたいだけでここまでくどくどと書いてきた。本論は目標の設定の仕方について言いたいのである。 春の選抜でぼろ負けをした文理野球部は甲子園優勝を目標に定めたという。これまで新潟の高校野球は甲子園一勝が目標だった。或いは甲子園出場だった。それを甲子園優勝と目標を定めたのだ。問題はここにある。筆者も高校三年の時、所属する登山部でインターハイ出場を目標にした。意外に思うかも知れないが、登山もスポーツ競技で高校総体や国体の競技になっているのである。クラブ仲間自体が意外な顔をした。だが筆者は至って大真面目で、それまでただ基礎体力作りに終始していた部活に大会を想定した勉強会を取り入れた。それだけで漫然とやっていた基礎体力作りが変わっていった。目標到達をまじめに考え出した。登山の愛好会から戦う登山部に変わっていった。残念ながら筆者の年は結果を出せなかったが、三年後に国体選手が出るようになった。 当時の筆者は高校生だから、目線の設定を意図的に高く変えようとしたのではなくて、戦う登山部はただの個人的な思い込みでしかなかった。それでも部員は真剣さから変わって行った。日常の何事につけても真剣に行うようになった。 全てはインターハイと国体に行くためであったが、真剣であることが面白いと思い出した。真剣であることは難儀ではあるが、難儀だからこそ楽しいのだということをそれぞれが感じ取りだしたのだった。こうなるとインターハイと国体に行くためではなく、真剣に難儀する楽しさのために、と目標が変わって行った。結果を出さねばならないのだが、要するに真剣であること、もっと言えば充実こそが最大の楽しさであると思い始めた。それが登山部の精神となっていった。そして当時の登山部の部員の一生の財産にもなった。 今回の文理高校野球部ではまだその意識は不統一だった。だが活躍した選手は真剣にプロ選手を目指していたようだ。だから監督のぶち挙げた甲子園優勝などと言う目標はまだまだ目線が下なのだった。自分としての野球の追求から見たら、甲子園優勝など情けないほど小さいものだ。甲子園に出てアピールできる自分のほうが遥かに大事なことで、だからこそ目先の緊張などにかまけていられなかったのだ。 大事なのは、そういった目線の想定は才能の有無にかかわらず、自分の作業・自己責任である事だ。目標は高く設定して真剣にチャレンジする。強く思うとはそういう事で、自分の独創として高い目標を設定する事だ。強く思うからこそ、色々な工夫が出てくるし、さまざまな見方も知ってゆく。高い目線の夢が叶うとは限らないが、粘ってゆく中で具体的に考えるようになる。具体的に考えるとは自分をも具体的に見れるということである。何より大切な『充実させ方』が判って来るのだ。 |
|講話集トップへ戻る| |
/トップ/定例活動/特別活動/講話集/今月の運勢/@Christy/