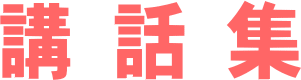|
命あるものは必ず果つる。思い上がったり迷いに惑わされる人間には認め難い事であってもこれは摂理である。ヒトも動物で命あるものの原則に入るから必ず果つる。個体は果てるのにヒトという種はずっと続いてきた。だから生命活動とは種の保存にあると言える。神がヒトに求めているのは種の連続であって、死は未知で怖いものだが不死を求めているのではない。
だが神は生命保存原則として疲労回復に苦痛を伴うシステムを作っても来た。疲労回復の為の苦痛を私達は症状と呼び、病気と呼んで嫌ってきた。症状や病気には苦痛があるのだから嫌われても仕方ないが、だがだからこそ動く事ができなく休まざるを得ず、その結果疲労回復という結果に導かれるシステムを神は授けている。
生きるとは苦痛を受ける事で、苦痛を受けていれば種の質を高めてその上で種を次代に連鎖させてゆける。ヒトという種の原始の姿では、いや全ての命あるものは、そのような苦痛の受け入れシステムを授けられていて今日まで種を絶やすことがなかった。
だが現実の医学はその苦痛を悪いものとして徹底的に嫌ってきた。苦痛や違和感は都合の悪いものだが、だが活動し適応力や疲労がピークに達する苦痛が生まれ、適応力や疲労が活動に対応できた時に苦痛は治まる。生きるとはそんな苦痛が日常的について回ることである。命は活動を繰り返す分苦痛が続き、それが稀な事ではない。痛みを持ち続ける事が生きる普段の状態と言える。それなのに医学はそんな痛みを普通の状態ではなく異常な事と考える。苦痛が不便ではあるが命の維持される姿なのにだ。
しかし、覚めてみると命のありようを都合や不都合という次元で見るのは医学だけでない。生きることそのものが都合や不都合という次元で行われてきたのだ。それが証拠にヒトは便利さをして幸せと呼んで疑問に思わないで来た。現代日本の便利度は世界有数なのに幸せと実感できない人が多いのは、便利が幸せではない事を皮膚感覚で判っているからだ。つまり、痛みが不都合な事であるのは誰も異議をはさまないが、その痛みを異常で不幸な事と考える生き方があって、だから医学は痛みと対決を続けて来た。考えてみれば判るが、どんな情報も活かすのは人の価値観であるから、痛みを敵視する医療技術も人の生きる目線の反映で間違いだったと言える。
その結果、種の質の低下を起した。要するにひ弱にさせてきた。自殺の増加がそうである。本来なら自ら縊る事は本能としてありえない。植物人間ですらも自ら縊る事しない。本能が生きようとさせている。それは理屈ではないのだ。生きているとはそういうことで、意識がなくても脳の原始の領域では死ぬ事を拒否するようにできている。それなのに自ら死ぬ事が出来るのが現代である。なぜ現代人の一部のヒトは本来出来ないはずの自殺が出来るのか。その理由はその人の脳の原始の領域が変質し殺されてしまっているからだ。
脳の原始の領域の死は薬による。薬は痛みを誤魔化すためにある。現代人は薬の有無に関係なく、痛みを遠ざける事を幸せとする。その結果、そういった後天的な脳の発達によってひ弱になって弱い種を生むようになった。それはヒトの持つ原始の逞しさ、死の回避本能を自ら殺したとも言える。
だがそんなひ弱を克服せねば治療にならない状況が起きるのは自然の流れで、苦痛を進んで取り入れるという治療も復活し出した。アレルギー疾患がそうだ。アレルギーを起す特定物質を今までは避けるようにしてきたが、少しずつ取り入れて免疫を作って治すというのだ。間違った反応でも反応こそ治癒の力と気づき、反応力から免疫を作って行こうというものだ。
この治療法の目線を覚めて見れば生きる事そのものである。要するに『知は痛み』である。何であれ痛みある生活が通常な人生でと思える様になった時、私達はその痛みを克服できてしまうようにできているのだ。刺激を受け入れ続けると大脳辺縁部と呼ばれる脳の原始の部分が発達し情感が生まれ磨かれ、人格が形成され、牽いては哲学まで作る…ここまで脳医学は解明できている。それはヒトという逞しい種が養われる道筋でもある
|