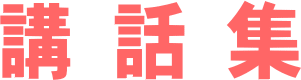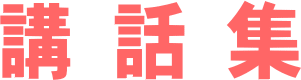|
新型コロナに振り回されて来て丸三年が過ぎて、四年目に入ろうとしているが、私達はコロナに対して慣れて来た。新型コロナがそう簡単に人を殺すものではなくなってきている皮膚感覚もあるが、要するにその皮膚感覚取得に時間がかかったという事だろう。
簡単な話で、結核という病気を思い起こせばわかる。昭和二十年代の生まれの人は、結核患者と暮らしてきた。床に伏している人も、そこから働きに出る人も、同じ家族として一緒に暮らしていたのだ。結核は特効薬のお蔭で激減したし、激減したればこそ、結核菌はその強度を増したが、収容施設も拡充することができた。昭和二十年代以前は医学の普及度が低かったためか、感染性の患者と家族とが一緒の生活をしていたのだった。
何を言いたいのか…、昭和二十年代の生まれの人はウイルスとの共存を余儀なくさせられた時代を生きて来たのである。現代は皮膚感覚でコロナが怖くなくなりだして、共存を恐れなくなったと言えよう。
医師や製薬会社や政治家が何と言おうが、庶民には感覚として見えてきている…終息は間近い、終息宣言をしても良いのではないか…と。 簡単な話、政治が終息を宣言すれば良い。それで済むのだ。それが出来ないでいる政治って何を意味するのだろう。政治家諸氏は、ヒトという存在が政治力で救える、と本気で思っておられるのだろうか…。不勉強すぎると思わないで、良いことをしているように錯覚し続けているではないか。
 筆者が不勉強と宣うのは、「哲学」に対して、である。件の哲学とは科学の根源を為すものである。その根源をを言葉の違和から探り出すものである。政治が哲学を基本に成り立っていないのは、それだけ政治家が言葉の違和に対する感性が鈍すぎる事しか意味しない。ヒトとはかくあるもの、という事を本では学べても、そんなものを哲学とは言わない。寧ろ市井の人々の感性の違和への拘りこそが立派な哲学なのだ。 筆者が不勉強と宣うのは、「哲学」に対して、である。件の哲学とは科学の根源を為すものである。その根源をを言葉の違和から探り出すものである。政治が哲学を基本に成り立っていないのは、それだけ政治家が言葉の違和に対する感性が鈍すぎる事しか意味しない。ヒトとはかくあるもの、という事を本では学べても、そんなものを哲学とは言わない。寧ろ市井の人々の感性の違和への拘りこそが立派な哲学なのだ。
それを省略して政治家なのに医学者の如き規制をし続けた。だが永遠にウイルスとは共存するものだから、政治の問題で、政治の問題だからこそ、全ての根源であるヒトが生きるとはという哲学に思いを発せねばならない問題だったはずだ。
医学的見地など本来不要なはずだった。ここに至って政治はコロナに対して何を救済したのか…という疑問を発すると、すべてが不明であった事に気づかねばならない。
政治が国を救ったのだとした場合、その国とは経済だけしか意味してなかったではないか。経済を受け入れるヒトには何も関係しなかった。必要以 外の経済を国民に押し付ける為に、政治はお金をばらまいた。 結局、スウェーデンが正解だった。スウェーデンはコロナに対して何もしなかった。だからすでに終息している。
醒めて考えれば判る原理なのだ。コロナにやられ放題やられたとしても、人は滅ぶわけではないのだ。ウィズコロナという言葉が如何にもらしく使われていたが、間違って使っている事に政治家は気づこうとしなかった。
それはこの国だけでなく世界の殆どが医学主導の施策で越えようとした。だが考えても見よ、どれほどの難病を治せたとしても人は必ず死ぬのだ。死ぬからヒトであり、人生なのだ。殊に新型コロナの場合、ウイルスを抑え込めたとしたら、その後にもっと強烈な殺傷力を持った恐ろしいウイルスが出現するのは決まっているのだ。世界は何を規制して何を治したのか。
流れに任せた結果、世界経済が破綻したとして、経済の破綻でしかなく人類の絶滅ではない。それが正解・正常な姿なのだ。それなのに、目先の経済をのみ守った、救ってもいないのだ。ノーコロナと言った国があるが、あれは逆に政治力の無さ、哲学の無さの証明だ。少なかろうが多かろうが、犠牲者の出る事がウイルス共存の姿だ。感染防止の小賢しい努力を正当に思うかどうか…無益ではなかったか。
ウイルスに任せておけば済んだ…。人口問題・地球破壊とウイルスを関連付ける政治家は極少だった。政治はなぜか経済を護ろうとした。経済ではなく、いつ死んでも悔いなしの生き方こそ正解と主張すべきだった。
|