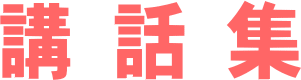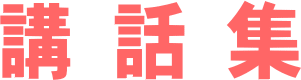|
どうせ人は死ぬ、いつか必ず死ぬ。それも全て為し終えてではなく、全てを中途半端のままにして死ぬ。中途半端で死なねばならない。これで良い、というポイントで死ねるヒトは、実は周りから疎まれている。大往生の死に方など、そのように疎まれているもののようだ。
死は殆どが、まだ中途半端なのに、という段階で訪れる。やり残しがあって未練があっても、死なねばならない。そこは誰でも平等に出来ている様だ。それなのに、死を恐れる。
自分の人生が中途半端でも、完全に仕上げたとしても、そこで終わるのだから怖くない事はない様だ。怖かろうがそうであるまいが、平等にいつか必ず死ぬのが人生と言える。 現代でも死は不合理になっているのに、高齢者を死なせないように、一日でも長く生きてもらうべく、ドクターは治療の主力を置いている。
死ぬのがヒトなのに、死なせないように運ぼうとする…。楽に死ぬのならまだ良いが、薬を用いて病室で生きている日を積み重ねる努力をさせられる。生き続ける努力を苦痛の中で続けさせられる…それは医者の独善でしかない。
これと逆に、意識が正常にあるのに、死を受け入れようとしない人も結構多く居られる。死ぬことが怖いという理由だけで、己が死を避けようとする。怖さを克服すべく努力しようとせず、一切を医者任せで済ませようとする。そうなると医者も神に化けてしまう。 死は避けられないのだからただ受けいれる、だけの事なのに、医者も患者も死ぬのが遅くなることを素晴らしいように錯覚するし、遅く死なせることが医者の腕の良さであるとお互いに思い込む…。
 筆者もそういう事に出くわした。父親の教祖先生の逝去の時だった。七十七歳で脳内出血を起こし、意識がなくなられた。二週間の昏睡状態の間に手足がチアノーゼを起きて、ここまでという事が三回あったが。その都度、息を盛り返された。 筆者もそういう事に出くわした。父親の教祖先生の逝去の時だった。七十七歳で脳内出血を起こし、意識がなくなられた。二週間の昏睡状態の間に手足がチアノーゼを起きて、ここまでという事が三回あったが。その都度、息を盛り返された。
九月一日、日曜日だった。日曜なのに主治医が回診に来られて、注射を打って戻られた。部屋を出て間もなく、ナースコールで心電図が止まった事を告げた。主治医は慌てる様子も見せず、死亡時刻を告げた…。終わった、と思いつつ、安堵した。何時死ぬか不明のままに苦しそうな呼吸をされている…それを見守る丈だが辛いものがあった。主治医の御臨終の声で、「先生も楽になられた」と心から思った。
死はこうして、全てが終わる。やり直す訳にゆかないのだから、恐れるのも当然ではある。未経験だから、恐れるのかもしれない。でも未経験だからこそ、受け入れざるを得ない。未経験であるから、自分から死を受け入れるしかない。
それを恐れるなと言っても、ヒトには死を回避する本能がある。その本能が死の怖さを増幅するようになっている。だが自分から受け入れねばならないのだ。
 滝打たれは、意識では死に赴く事にして覚悟を決めたとしても、それは覚悟でしかない。滝打たれでなく、己が生理の死も自ら受け入れるしか方法はないのだ。どうせ・いつか・必ず…は避けられないのだから。 滝打たれは、意識では死に赴く事にして覚悟を決めたとしても、それは覚悟でしかない。滝打たれでなく、己が生理の死も自ら受け入れるしか方法はないのだ。どうせ・いつか・必ず…は避けられないのだから。
どうせ・いつか・必ず…は避けられないのだから、だからこそ常に毅然として行動せねばならない。
毅然と行動をし続ける…とは、命あることが有難いとか嬉しいとかではなく、毅然と行動をすることが生きる姿でしかないからだ。
どうせ・いつか・必ずは安心を産む。それなのに、恐れて生きよう、生き延びようとする。どうせ・いつか・必ずを忘れていると体を張って生きて行けなくなる。生きるとは体で感じる事で、学びと同じだ。永遠に生きられるとして何を行う・何を学ぶのか
死ぬ事を意識しないでのびやかに生きる…は無い。生きることが充実していないと、死は実態を伴わず降りかかる。未経験で不可解だから、ヒトの今を充実させようとする。その充実も人それぞれではあるが、伸びやかさを伴う生き方になる。
伸びやかさを忘れて生きても生きたことにならない。筆者としてはそうでありたくはないのだが
|