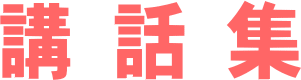|
今年7月の御嶽夏登拝は、覚悟を強くして御嶽に臨んだ。何の覚悟かと言えば「やり切る」という事であった。昨年末に手術をし、筆者の健康状態は術前に戻ったつもりでいたが、腰中心に術前とは大きく異なる感覚があった。というか、今までの状態の違和と違う違和を多く感じていた。腰が腰の役割を果たしていないように感じていた。加えて登拝の2週前には、食べられなくなって、肩で呼吸をする様になっていた。「それが老化と言う事だもの、工夫するしかないさ」と思って登拝の準備をしていた。我が身が今まで通りに処理できようがない事は予知できていた。ともあれ、食べれない事からも解放され、登拝の日を迎える事が出来た。
術前と何が変わったかと言うと、一人を覚悟した、という事だった。今までは周りの方々の世話を焼くことが出来た。世話を焼かせていただく力があった。今回は或いは世話を焼いていただく側に廻るのかもしれない…という思いがあった。その時に「一人でやる・やり切る」という覚悟が大事だと思っていた。速さとか能力は往年に比べようがない…このことは受け入れねばならない事と思っていた。安直に助けに応じるのではなく、まず一人でやり切る事だと思った。一人でやり切るとは、その苦しさを普通の事と思う事から始まると思った。
登拝当日、7合から8合目までは違和なく足を運べた。8合目の女人堂から歩き出して間もなく腿に痙攣が起こりだした。この腿の痙攣は8合半の明治不動までは工夫する事が出来た。高低差30センチ以内の場所を探して足を置いて歩を進めると負担が少ない事に気づけたからだ。だがその足の置き場を探すのに、時間がかかるのだった。その結果、皆さんに後れを取るようになった。
 「先に行って下さい。必ず行くから」と集団から遅れる事を伝えた。(いよいよ、いつか来る日となったか)と思いながらも、焦る事は無かった。自分なりに『最悪』を想定していて、それがいよいよは免れない事だと予期していたからだ。いよいよ「いつか来る日」の本番に臨む日になったと思い、だから誤魔化すことなく余力がなくなる迄、やり切ろう。と思った。 「先に行って下さい。必ず行くから」と集団から遅れる事を伝えた。(いよいよ、いつか来る日となったか)と思いながらも、焦る事は無かった。自分なりに『最悪』を想定していて、それがいよいよは免れない事だと予期していたからだ。いよいよ「いつか来る日」の本番に臨む日になったと思い、だから誤魔化すことなく余力がなくなる迄、やり切ろう。と思った。
大先達の高橋君の「六根清浄」の声と、それに呼応するみなさんの声がだんだん遠くに聞こえるようになってゆくが、特に何とも思わなかった。或いは最後の御嶽登拝かも、という思いはあったが、いずれ通る道、御嶽に登拝を拒否される日になったんだなあ、という思いだけがあって、それ以上の事は浮かばなかった。ただ只管、足場の良いところを探して進もう…だけだった。絶対不調というものと個人が闘うだけだった。
御嶽と言う山は、標高は高いが、8合目半まではゆったりとした緩斜面の山だ。そこを登って行って8合目半に至ると斜面が急にせせりあがって、首を無理やり上に向けないと稜線が見えなくなる。その急斜面まで登れたという思いが湧いた。
 登れることが修行ではなくて、登ろうとすることが修行だ、と言って来たことが自分に番が回って来た…苦しさを当たり前にして、それを普通に臨むだけだった。 登れることが修行ではなくて、登ろうとすることが修行だ、と言って来たことが自分に番が回って来た…苦しさを当たり前にして、それを普通に臨むだけだった。
顔を上げて前を見たら、前方の集団の最後尾にいた岩淵さんが集団に近づき、追い越しているのが判った。石室小屋に一番乗りになるであろう、とは想像したが、まずは自分の歩く事だけで精いっぱいだった。9合目にある石室小屋下の石積の道が、黒沢ルートの最も難所である。焦る必要もあるまい、今の一歩に集中する事だ、気持ちだけは余計な事は考えず進んだ。落ち着くというより、なぜか平坦な思いだった。
「先生、荷物下さい」。岩淵さんの声だった。早歩きして自分の荷を小屋に置いて、戻って来られたのだった。ここはありがたく、荷を背負っていただくのが正しかろう…と思った。皆がへばって苦しいのに、と思うと自分が意固地になっている事は宜しくないと思えた。素直に感謝出来た不思議があった。何より、いつか来る日を自力で迎えられた事…きっちりと迎えねばならないという覚悟だけは明確だった。でもそれをお山で迎えられて嬉しかった
|